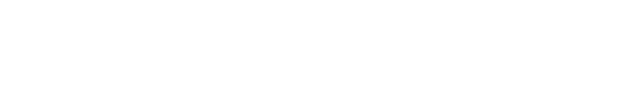肝機能障害と言われたら
肝機能障害の経過を確認します
肝機能障害を来す原因にはさまざまなものがありますが、急性の経過をたどるものと慢性の経過をたどるもの、急性の経過も慢性の経過も取りうるものがあります。これまでの検査結果などを確認して、経過によって原因を探る検査を組み立てます(血液検査や画像検査)。急性の経過なら急激な悪化の兆候がないか?慢性の経過による蓄積ダメージの程度はどれほどか?を確かめます。
沈黙の臓器が悲鳴をあげてしまうと・・・
慢性の肝臓の炎症による蓄積したダメージによって、肝臓は線維化(徐々に硬くなる)していきます。線維化が進んだ状況が肝硬変です。肝硬変になると肝臓が本来の働きを発揮できなくなっていきます。肝硬変になっても初期段階では症状が目立ちません。肝硬変がさらに進行してしまうと、肝臓はさまざまな働きをしているので、色々な不調が出現します。肝臓に入る血管の圧が高まり、それによる症状も出現します。肝臓がんもできやすくなってしまいます。症状としては黄疸、体のかゆみ、むくみ、腹水、胃や食道の静脈瘤、意識障害、血が止まりにくくなったり、感染症にかかりやすくなったり。こういった症状がはっきりと出てくるのは、肝硬変でも進行した状況になってからなので、肝臓は沈黙の臓器と言われています。沈黙の臓器が悲鳴をあげる前に、肝臓を線維化(硬くさせてしまう)の原因を改善することが大切です。
原因はアルコールや太りすぎのせいにして良いのか?
確かに飲酒量は多いし、肥満はあるが、例えばB型肝炎ウィルスのような治療を要する原因も重なっていることに気づかなかった場合、肥満のせいにしていて肝臓のダメージは蓄積されてしまうことになります。また近しい人を感染させてしまうこともあるかもしれません。なので、これまで検査歴のない方には、一般的な肝機能障害の原因になりうる項目(B型肝炎やC型肝炎、免疫の異常、ホルモンの異常など)の血液検査を実施しています。また、肝臓の出来物(腫瘍など)が原因で肝機能障害がでることもあるので、画像検査も確認したいところです。